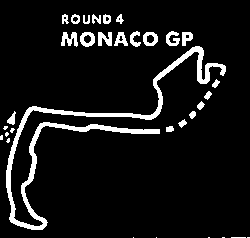
サンマリノグランプリ以降、氷河は、とりあえず女遊びを避け、ひたすら鬱々として日々を過ごしてきた。 結局、夕食の誘いを拒まれたあの日以後、瞬に会う機会は持てず、更に情けないことに、氷河は、瞬に関する情報を得るために紫龍や星矢に頼るしかなかったのである。 こういうことにドライバーのプライドの高さは無関係なのではあろうが、氷河は その事態に苛立ちと憤りを禁じ得なかった。 「ああ、最初はさ、チーム内にも、兄の七光りとかって、結構瞬に対する反感もあったらしいんだけどさ。でも、瞬って、あの通り可愛いし、確実にポイント稼いでるだろ。今はみんなに可愛がられてるみたいだぜ。なにしろ一輝があの通り“サーキットの独裁者”だもんで、監督以外、あんまりきついこと言えずにいたらしいんだよな。そこに瞬が入ってきて、瞬はスタッフの言うことよく聞くし、控えめだし、素直だし、一輝がまた瞬には甘いらしくてさ、今までチーム内がぎくしゃくしてたのが、瞬を潤滑油にして、すごく風通しのいいチームになってるみたいだった。みんな、口を揃えて、瞬は拾い物だったって言ってたぜ」 (控えめで素直だと……? 俺に対する態度とは随分違うじゃないか……!) 「まあ、それは当然のことだろうな。瞬は、たった3戦で、昨シーズンのセカンド・ドライバーが全16戦で稼いだポイントの4分の3を稼いでしまったんだから。ここは、なにより実力が物を言う世界だ」 紫龍が、星矢の言葉に相槌を打つ。 「なんたって可愛いもんなー。その趣味ない奴だってぐらぐらするよな。あそこのメカニックたち、ちょっと危なそうな奴もいたし、他チームのドライバーが瞬に迫って、一輝に無能呼ばわりされたって話もあるし」 (そんな奴等がいるから、瞬も俺に対する警戒心を解かんのだっ!) 「珍しいことを言うな、星矢。マシンがいちばん可愛い主義のおまえが」 「そっかぁ? でも、ピンクの軽自動車みたいで可愛いじゃんか、瞬って」 「おまえ、その表現、どーにかならんか。普通、花とか小動物に例えて言うものだろう、その手のことは」 「えーっ、俺の最高級の誉め言葉だぜ、これって」 「とてもそうは聞こえん」 (見かけはピンクの軽自動車でも、中身は真紅の いずれにしても、氷河以外の人間に対しては、瞬の人当たりは随分やわらかいものであるらしい。 星矢たちの話に、氷河は何やら胸がムカムカしてきてしまったのだった。 苛立ち、ムカつきながら、それでも、瞬に関することを知りたいの一念で、氷河はさりげなくピットの隅で彼等の会話に耳を傾けていた。 そこに、顔馴染みの広報マンがひょっこりと姿を現わす。 氷河の影を見付け、彼はピットの中にぴょこぴょこと入ってきた。 「やっと見付けたぞ、氷河! 今夜の相手は決まっているのか? 紹介したい娘がいるんだが」 「……!」 それでなくてもいらついていたところに、馬鹿なファン・サービス話を持ってこられて、氷河の脳はぐらぐらと沸騰しまくってしまったのである。 「貴様、知らんのか! 今期、俺は毎晩マシンと寝ることにしてるんだ! 俺にあてがおうというのなら、真っ赤なフェラーリでも連れてこい!」 氷河の怒声に、その広報マンだけでなく、紫龍、星矢までが驚いて目を丸くする。 信じられないセリフを聞いてしまったと言わんばかりの彼等三人の態度に腹を立て、氷河はそのままドカドカと大股でピットを後にしたのだった。 が、その腹立ちは、1分と経たないうちに、氷河の中から消えていってしまったのである。 もしかすると、こういう誘惑は瞬の許にも及んでいるのだろうか? 自分自身のこれまでの行状を棚にあげ、氷河は急に心配になってきてしまったのだった。 一輝には婚約者がいるという話であるから、その手の誘惑は、プロジェクトHSでは瞬の方に集中することになるだろう。 不安にかられた氷河は、ピットロードをプロジェクトHSのピットに向かって脱兎の勢いで駆け出していた。 公式予選の1日目、またしても暫定1位の座は瞬が占めていたせいもあって、プロジェクトHSのピットにはマスコミ関係者が何人かたむろしていたが、傍から見ている限りでは、一輝がしっかりと弟をガードしているようだった。 (……あれなら大丈夫そうだ) ほっと安堵の息を洩らし、洩らしてから氷河は、自分が何にほっとしているのかを訝った。 (──しかし、あの子が脳みそが胸にいったような女より魅力的なのは事実だ) 一輝の陰に隠れ、唇を引き結んでいる瞬の姿を見ているだけで、心がなごんでいく。 さすがの氷河も、ここまで正直な自らの心に向かい合うことになってしまっては、自分の内に生れつつある感情を素直に認めざるを得ない。 そして、それを認めてしまったら、あとはその感情に従う以外、氷河には為す術がなかった。 「氷河の方が追いかけているというのは珍しいな。奴にしてはいい趣味だが、ちょっとまずいんじゃないか。なにしろ、相手が相手だ」 氷河の姿がかき消えたピットで、マシンの内部をいじくりまわしながら、紫龍がぼやく。 星矢はマシンのフロントノーズを撫であげながら憂鬱そうな顔を作った。 「俺、やだなー。瞬ってさあ、自分のマシン、すっごく可愛いがってるだろ。一輝や氷河みたく偉そうに構えてもいなくて、人当たりはいいし、優しいし、氷河が勝手にクラッシュさせたマシンのこともかわいそうなことしたって申し訳なさそうにしてたし。俺、氷河になんか構ってほしくないんだよな。氷河にはもったいないんだよな」 「なんだ、また氷河が何かしたのか」 星矢が氷河を責めるのは、大抵、氷河がマシンを手荒に扱った時と相場が決まっている。 今日の予選で、氷河はマシンを壊したりはしていないので、何が星矢を苛立たせているのか、紫龍には その見当がつかなかった。 「タイムが伸びないって言って、氷河の奴、さっきマシンを蹴飛ばしやがったんだ! 俺、あいつをブッ殺してやろうかと思ったぜ!」 星矢の話を聞いた途端、星矢の怒りは紫龍のものになった。 丹精込めてセットアップしたマシンは、メカニックマンにとっては我が子も同然である。 自分の子供を足蹴にされて、黙っていられる親がこの世にいるだろうか。 「よし、星矢。瞬に、氷河のこれまでの悪行をすべて告げ口してやろう。瞬と、俺たちのマシンのために、これは瞬の友人としての俺たちの義務だ」 「おー、俺、そういうことなら頑張るぞーっ!」 彼等は何よりもマシンを愛しており、彼等のマシンの敵は彼等の敵なのである。 日頃の悪い行ないが、氷河の恋路に目一杯暗い影を落としていた。
|
【next】