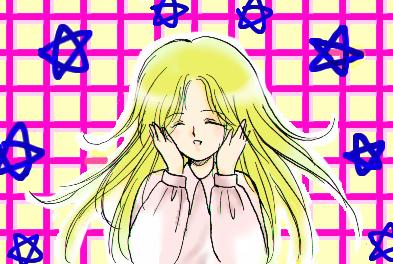「瞬ちゃん、いらっしゃい。キャンプは楽しかった?」 可愛い瞬ちゃんがすっかりお気に召していたマーマは、お泊まりにやってきた瞬ちゃんを、ロシアのお友達を押しのけて、満面の笑顔で出迎えました。 「はい、びっくりしちゃった。氷河ってば、急に僕を暗がりに連れ込んで、『俺のために、毎朝みそ汁を作ってくれ』なんて言うんだもの。僕、おみそ汁なんて作ったことないから、とっても困っちゃったの……」 「まあ、そうなの……。変ねえ、日本の男はみんなそう言ってプロポーズするんだって本に書いてあったのに……」 内心舌打ちをしながら、マーマはそう呟きました。 「え?」 「いいえ、何でもないのよ。瞬ちゃん、ケーキがあるから、食べてちょうだい」 「わあ、ありがとうございますv」 マーマは、適当にその場をごまかして、瞬ちゃんを応接間に連れて行きました。 あとから、てこてことロシアのお友達もついてきます。 瞬ちゃんの前にお手製の可愛いケーキを置きながら、マーマは、にこにこしながら言いました。 「瞬ちゃんがお泊まりに来てくれて嬉しいわ。氷河と二人きりだから、この家はいつも静かで寂しいのよ」 「え……」 瞬ちゃんがロシアのお友達のお家を訪ねたのは、まだ今日で2回目。 お泊まりは初めてです。 ですから、瞬ちゃんは、ロシアのお友達のお家で、ロシアのお友達のお父さんに会わないことを不思議に思っていませんでした。 お父さんは、お昼の間はお仕事に行っているものですからね。 でも、そうだったのです。 ロシアのお友達には、お父さんがいなかったのです。 瞬ちゃんにも、お父さんとお母さんがいませんでした。 そして、瞬ちゃんも、無口なお兄さんと二人暮らしでした。 ですから、マーマの言葉を聞いて、瞬ちゃんはロシアのお友達に親近感を抱いてしまったのです。 「瞬ちゃんもご両親がいないんですって? 氷河と仲良くしてやってちょうだいね。私のこともマーマって呼んでね」 「は…はい。えと、あの、マーマ……」 「まあぁぁぁぁぁvvv」 瞬ちゃんが、遠慮がちに、ロシアのお友達のマーマを『マーマ』と呼ぶと、マーマは大感激。
「あ……あのね、瞬ちゃん」 マーマは、感激のあまり、ちょっとどもり気味です。 「ウチには、ほんとはちゃんとお客様用のお部屋もあるんだけど、初めてお泊まりする家で一人で眠るのは心細いでしょう? だから、瞬ちゃん、今夜は氷河と同じベッドで眠ってちょうだいね」 「はい、僕、寝相はいいです」 「氷河はちょっと悪いんだけど、でも、平気よ。どうせ、氷河は朝まで眠れっこないんだから」 「え?」 瞬ちゃんが不思議そうな顔をすると、マーマは慌ててぷるぷる頭を横に振りました。 「いいえ、こっちのことよ。ケーキ、おいしい?」 「はい、すっごくおいしいですv」 「…………」 瞬ちゃんが嬉しそうに頷くと、それまでマーマの迫力に押されて黙って瞬ちゃんの横に座っていたロシアのお友達が、無言で自分の分のケーキを瞬ちゃんに差し出しました。 |
【next】